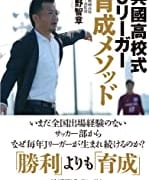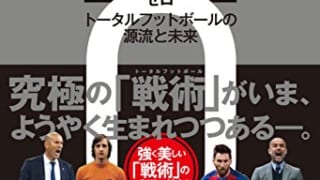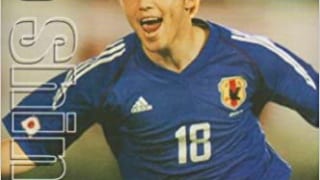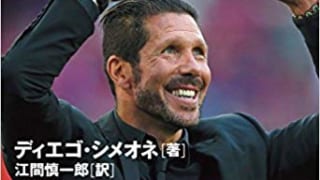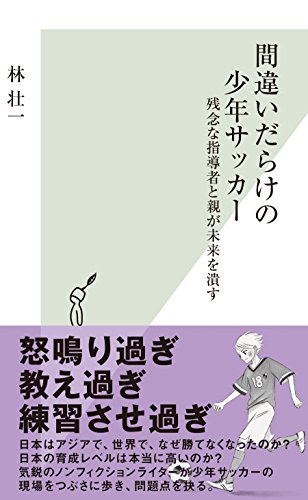インテルは6年間選手を育てて8100万ユーロ(約100億円)を手にしたそうだ。その筆頭はバロテッリの3000万ユーロ(約35億円)。
さらにインテルアカデミーからは半分の子供がプロになっているという。もしそれが本当ならば驚異的な数字である――。
アメリカ文化のルポに詳しい林壮一は元プロボクシングのライセンスを持つノンフィクション作家。
刊行年の2015年、アギーレはアジアカップで決勝トーナメント1回戦負け(ただしシュートは35本)で解任された。続くハリーも中国、韓国、北朝鮮と相対した東アジアカップで勝ち星なしと寂しい結果。表紙に謳われるキャッチコピー、「アジアでなぜ勝てなくなったのか」だけを見るとそれを揶揄した内容に見えなくない。
しかし冒頭で「少年たちがどうすればサッカーを愛し続けられるか」を探ると明言する。まず底辺の少年団をそれらしく描いて危機感をあおり、ドラマティックに読ませていく手腕はさすがアメリカの下層文化を鋭く描くルポライターと言ったところ。
リズムよく内容は「OneTokyo」の要職としても知られる鈴木良介、ドルトムントトサッカースクール世田谷などとインタビュー。ドルトムントではパスよりシュートを選ばせるそうだ。
ACミランの下部組織は週3~週5。リフティング練習あり、強度は強めとか。
「情熱と決意を持ったタイプしか成功できない」
とはいえACミランもインテルの下部組織も、大成する選手の結論は結局選手の気持ち。ちなみにインテルはセレクションを行わず、スカウトした選手を練習に混ぜているらしい。
浦和レッズは得意を伸ばし、ヴェルディは他のスポーツも推奨する。
元レッズのエクスデロによるとアルゼンチン人はもっと練習するそうだ。
ちなみにエクスデロは息子をお父さんコーチにつぶされそうになったからとアルゼンチンに帰国したと言う……。ちなみに、この息子はU23にも選出され、15年以上のプロ生活を続けるエクスデロ競飛王その人である。
連載をまとめた書籍だから必ずしもタイトルに沿った内容がなされているわけでもない。
どちらかというとサッカーを知らない大人を含めた自己啓発本といったテイ。もとの媒体は小説宝石で、それはマルセイユルーレットにわざわざ「という技」とつけたことからもうかがえる。
ほかにも「サッカー本」としては微妙な表現があるのはご愛敬。お父さんコーチについてある種の危機を謳ってはいるが、それについての解決策は特に提示されていない。
しかし筆致は美しいし、インテルやエクスデロなどによる貴重な証言もある。
エクスデロは埼玉栄高校の総監督として選手権を憂愁に導いてもいる。
■本書で得られる知見
- 日本の少年はアルゼンチンより練習量が少なく、イングランドよりは多い。
- インテルのシュート練習は必ず逆方向を狙わせる。
- 伸びる選手が持っているのは自分で考えて行動できるゆるぎない情熱。
- お父さんコーチの指導は2015年時点ではまだ高くないらしい。
(細かい内容は本書でぜひどうぞ!)