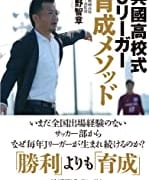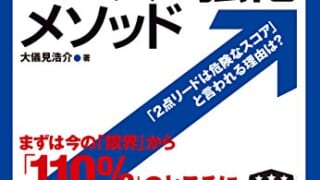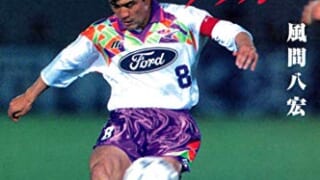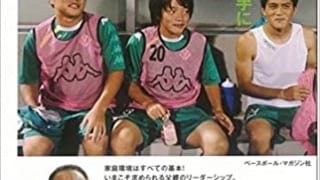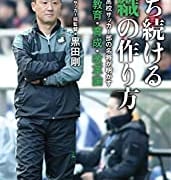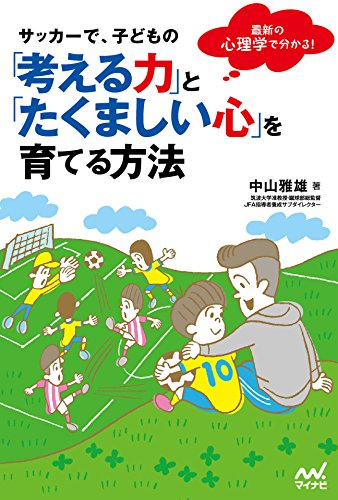こんにちは、新井一二三です。
今回は数々の名プレイヤーを輩出し、日本サッカー界の要人を世に送り出し続ける名門中の名門、筑波大学サッカー部総監督である中山雅雄の「サッカーで、子供の「考える力」と「たくましい心」を育てる方法」を紹介します。
◇
サッカーをケーブルテレビや衛星放送で楽しむ好事家ならおなじみ、内牧敦子のイラストが目を引くサッカー育成書。
筑波大学ときて「中山雅」と聞けば当然「中山雅史」を思い浮かべるが、本著は「中山雅雄」。名門筑波大学サッカー部の総監督でJFAキッズプログラムの検討、作成から指導も行う、とされているからいわゆる「筑波派閥」に属する日本サッカー界の大大重鎮といってもいいだろう。この人に気に入られれば、ナショナルトレセンになれる。そう目されてもおかしくない立場の人、が書いた書籍ということになる。
しかし本を開くと驚いた。なにしろ異常に読みにくい! それは文字の質でなく、文字の大きさとか、いわゆる装丁の問題なのだが、なにしろ内牧敦子からくるイメージとはかけ離れていて驚いてしまう。表紙にはマイナビとあるが、カンゼンが編集したらこうはならなかっただろう。
とはいえ、読みにくい事をかいつまむのが書評の良さと考えれば意欲もわく。なんでも本書はJFAの機関紙6年分のコラムの集大成らしい。
本書は彼自身の意見をスポーツ科学の権威たちの言葉をかりてその論を補強し、成立されることで進んでいく。
たとえば「注意深く組み立てられた練習を1万時間以上行えば、だれでもその分野のエキスパートになれる」、というのはyouber「進撃のy」も言及しているところではあるが、あくまで「いかにコーチングするか」、「コーチングの質」に言及しているところが面白い。
小学年代では「認めて、与えて、教えない」が主流だとは思うから、JFAのプロフェッサーの言葉とすればちょっと異質な感じもする。まぁ、教授が「教えない」を売りにすれば自己否定になりかねないのだけれども。
重鎮が語る独自の育成論、トレセン論
しかし、「指導者の一番の役割は、子供たちがゲームで楽しくプレーできるように技能を身に着けさせる」という言葉には驚いた。驚愕したと言ってもいい。これは「サッカーは上手くならないと楽しめない」と言っているのと同じ。サッカーが「する」のも「観る」のも娯楽性においてほかのゲームより劣っているのは同感だが、JFAの教授がこれを断言してしまうのには恐れ入った。僕は「だったらその上で普及をどうするのか?」を考える。
正直に言って、構成を放棄したしたような編集方針に加え、トレセンを「よりサッカーの上達機会を目的とした取り組み」、と謳うのは現場の感覚とは大きく乖離していると思う。むしろトレセンは「各世代の日本代表をあぶりだす、ふるい」と形容してしまった方が周囲にも理解されるのではないか。「上達機会」が目的ならセレクションは必要ないと思うのは自然なことのはず。
しかし、サッカーについて「ある種の基本」がちりばめられているのは間違いない。隔月の連載をまとめた書籍だから、内容に一貫性がない部分がある。それはつまり本書が「サッカーで、子供の考える力とたくましい心を育てる方法」と直結しているとはいいがたいということ。
しかし、内容とタイトルが乖離しているのはサッカー本では「あるある」。それだけにバラエティに富んだ記事構成になったとポジティブに考えたい。「フロー」の説明であえて「ゾーン」という言葉を使わなかったことなどにも一種の矜持がうかがえる(ゾーンは小池一夫の造語に近い)。機関紙に堂々と連載されていたことだけはあり、サッカー人たちへの基本の一冊としての含蓄は整えられている。
■本書で得られる知見
- サッカーで大切なのは「自尊心」
- 大切なのは成功体験
- 自分の能力に応じた課題に挑戦するときフローは起こる。
- 工夫しながら身に着けた技術は忘れない
- インターバルを短くする工夫をしよう
- スポーツは常に挑戦
(細かい内容はぜひ本書でお確かめください)