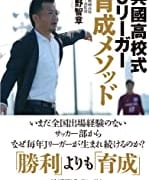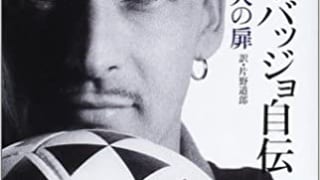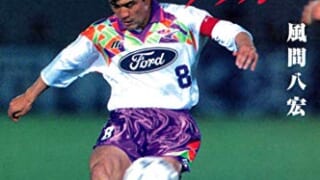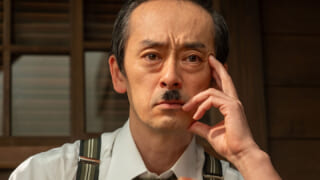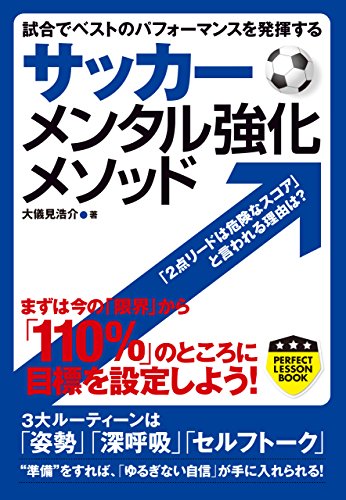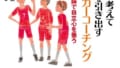こんにちは、新井一二三です。今回は株式会社メンタリスタ代表取締役であり、東海大一高時代には主将として鈴木啓太とサッカー部に所属。現在は「メンタルトレーニングコーチ」として活躍する大儀見浩介著、「試合でのベストパフォーマンスを発揮する サッカーメンタル強化メソッド」を紹介します。
◇
まず初めに断っておきたいが、本書はまぎれもなく良書である。
いや良書というより「とても価値のある一冊」と表現したほうがいいかもしれない。
少なくとも、得られる知見は今までに紹介したサッカー本の中では圧倒的なナンバーワンである。
しかしのっけから「モチベーションがなければメンタル面のテクニックをいくらつけても宝の持ち腐れ」、と始まる。書名は「サッカーメンタル強化メソッド」だからいきなりの自己矛盾をとらえられかねない書き出しである。いったいどういうことなの……。
冒頭から刺激的な導入ではあるが、結局自分からやる気を出して練習しないと効果がない、とうことなのだろう。
とはいえ次の項目では「最初は外発的動機付けスタートでもかまわない」と自分とは正反対の論を投げかける。
つまり、少なくとも「ドリブルは○○%成功する」とか「サッカーはチームスポーツだから小1からグループ練習メインでないと上達しない」などという、うさんくさい自己啓発セミナーばりの催眠誘導テクニックを駆使した本ではない。
対抗の論もあぶりだしながら、その効果「メンタル強化メソッド」を展開していくきわめて良識的な本、ということになる。
もちろん「最初は外発的動機付けでいい」という論はサッカーを息子たちに「促した」親御さんたちへのフォローととらえる向きもあるだろうが、それにしても自己矛盾をおこしかねない一文を投入した勇気は好感に値する。
選手と指導者へのアプローチがうねりだし、名言のオンパレード
しかし、読み進めるにつれどうにも雲行きが怪しくなってくる。
例えば選手は「最初はやらされていても」そのうち「もっとうまくなりたい」というモチベーションに変化させることができるという。では「もっとうまくなりたい」というモチベーションとなんだろう? 勝ちたいは、わかる。負けたくない、もわかる。その「もっとうまくなりたい」というものが何であるかに説明はない。それはすべての選手にあるものなのだろうか。
どうにも、ちぐはぐした構成に気を取られてしまう。
どうも本書の前半は「メンタル強化の方法を教えたい指導者向け」でなく「メンタルを強化したい選手向け」の本であるように見える。確かに「最初はやらされて」いて、「もっとうまくなりたいと思う選手」には効果的な論だろう。
ならば「メソッド」などというわかりにくい言葉を使わずとも良かったのに……とは思う。装丁と内容のズレがどうにも惜しく感じてしまう。
しかし後半からは、簡単に言えば「名言のオンパレード」が始まる。
おそらく構成としては前半がトークセッションの口述筆記、後半が自身による筆致なのだろうか。少なくとも前半と後半で目的とする論の着地点、そして対象としている層がまるで違う。
正直編集者としての見方をすれば、前半をカットするか、最低でも前半と後半の内容を入れ替えるべきだったのでは、と思う。
それほど、含蓄のある後半に本書の真価を感じる。著者がさまざまな知見を得て紹介した「メンタルメソッド」の数々は、巻末に圧倒的な数が記載された参考文献や研鑽の中から編まれたものなのだろう。
それらを、現在のサッカー指導シーンになぞらえながら、なにが必要で、なにが必要でないかを明文化してもらえればもっと良かったとは思う。なぜそう「成」らなかったのか。
表紙に謳うキャッチコピーも、いまひとつ内容と噛んでいない気がする。それはサッカー本界隈の「あるある」だとはいえ、なんとも謎多き一冊とも言えそうだ。
■本書で得られる知見
- イメトレは大事(準備運動の時にするとよい)
- センスがいいは「相手の嫌がることをできる」ということ
- 音楽で気持ちを条件付けできる
- 「自信」の対義語は「危惧」
- 試合直前には言葉を「フォーカス」しよう
- 深呼吸は先に息を吐く
- プラス思考を作らないと人間の身体は動かない
- 試合会場は下見しよう
- 指導者は選手の自信を構築しよう
- リーダーが必要なのは聞くスキル
(細かい内容はぜひ本書でお確かめください)