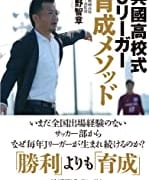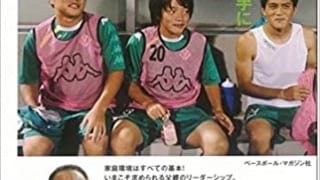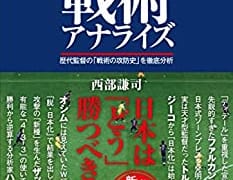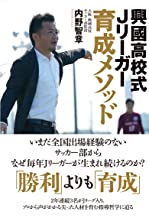稀代の監督が語る、プロ内定選手に共通するもの。
南野拓実は高校時代、年度代別代表にも選ばれるエリートであったにもかかわらず、まじめで謙虚。常にどうすれば自己を高められるかを考えていた評判の生徒だったという。そんな彼が過ごした興国高校を率いる内野監督。彼がサッカー部の監督に就任した時、部員はたったの12名。しかしその後、年に一人以上のペースでプロ選手を輩出している。その排出率はJ下部組織も驚愕のレベルである。しかも、興国高校はほとんど全国大会にも出場していない。
高校部活の育成は、実質2年しかない。内野は著書で勝利よりもはっきりと育成……プロ選手を送り出すことだと言う。そして実際、その2年という時間的制約の中でプロ選手を続々排出する。その中の多くは、小学時代すらトレセンに入っていない選手もいるという。むしろ、内野はトレセンについて否定的だ。
南野は別格だとしても、いい選手にはトレセンに行かせないというのだから驚きだ。トレセン入りをすれば選手は天狗になる。その天狗の鼻が選手の成長を妨げるというわけ。結局のところ、興国高校にくる生徒はどこかしらで挫折を経験した選手。しかし、その挫折こそがハングリー精神を生み、自己が成長する原動力となるという。さらにいえばプロ入りする選手はサッカーが大好き。なるほど興国高校サッカー部のスローガンは「ENJOY FOOTBOOL」である。たぶんトレセンは選手にとってENJOYじゃない。
内野監督に垣間見える合理性と魅力。
内野はまた、選手育成において「高校」という組織のメリットを多くあげている。わかりやすくいえば、スポーツ高校である自校の先生には各分野のプロフェッショナルがいる。彼らの協力を仰げば、合理的で総合的な強化できる。ちまたの監督はえてして自分以外の息がかかることを嫌うが、内野にはそれがない。外部コーチの招へいにも積極的である。それは哲学的というよりも、たった2年で選手を育てなくてはいけない、そのためにとった合理的な戦略と見える。
内野はまた、高校年代での指導者の質にも言及している。いまや、中学年代のクラブチームの多くが合理的な指導にとりくんでいる。しかし、高校年代になるとどうか……。選手の中には、興国高校の指導体系に魅力を感じて入学するものもいるという。
夏休みは海へ行け、彼女を作れ!?
内田は、彼女を積極的に作れという。一見すると破天荒に聞こえるが、内野は高校年代でそういった経験をしないことで、ゆくゆくつぶれていく選手を目の当たりにした。その言葉にはある種の影も感じさせるが、だから選手権には彼女を連れてこいと内野は屈託ない。
著書、興國高校式Jリーガー育成メソッド ~いまだ全国出場経験のないサッカー部からなぜ毎年Jリーガーが生まれ続けるのか?~ ヤケに長いタイトルだが内容は口述形式で読みやすく、さらに家庭と選手の向き合い方や、日本人が欧米人に秀でるスタミナやメンタリティ、そこで日本人がプロとして生きていくヒントをかいま見せ、内容はさらにサッカークラブのマネジメント面にも及ぶ。その内容について驚嘆すべきは、それぞれについて明確は答えが示されていること。育成になぞかけなんて必要ないということか。さらに、若き日の稲本や新井場の様子も描かれている。そして、エコノメソッドはすごいらしい。
また、内野は、のし上がるためにハングリー精神は必要だが、劣等感は必要ないと説いている。生徒に劣等感を与えるのはいったい誰なのだろう? ちなみに、興国高校が全国大会に初出場するのはまさかの2020年。しかし、それまでに輩出したプロ選手は20とも言われている。
■本書で得られる知見
- 日本人が欧米人に秀でるのはスタミナと敏捷性と精神力。
- リフティングは大事
- 劣等感は必要ない
- 高校育成の時間は2年位しかない
- 彼女は作った方がいい
(内容の詳細は本書でぜひどうぞ!)
興国初優勝!練習動画も!関連動画は次のページから。