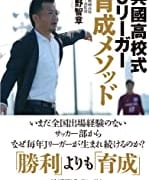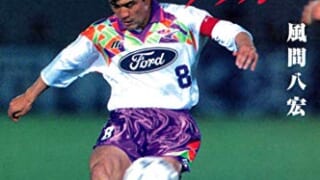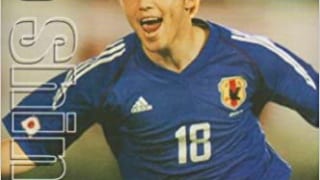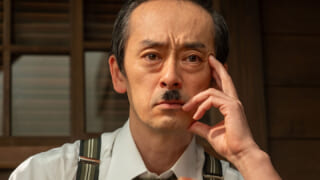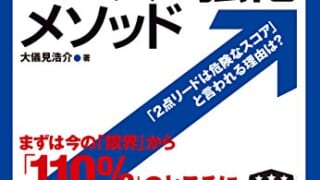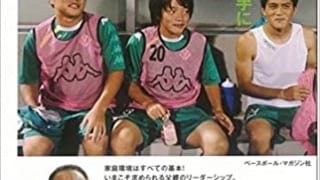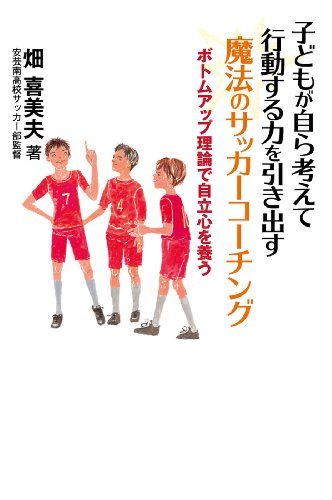こんにちは、新井一二三です。今回は広島観音高校を全国でも有数の強豪高校に導いた畑喜美夫の著書、「子どもが自ら考えて行動する力を引き出す 魔法のサッカーコーチング ボトムアップ理論で自立心を養う」を紹介したいと思います。
◇
2006年、広島県でそれまでまったくの無名高校だった広島観音高校をインターハイで初出場からいきなり初優勝。その後選手権でもベスト8、プレミアリーグにすらチームを導いた畑喜美夫による著書。
確かに偉業である。しかし本書で畑はあくまで「選手が主役」で自分は「アドバイスに徹した」と断言する。しかし戦果を耳にした各地の指導者によると、畑ですら思いもよらず画期的な指導法だったという。それが表紙にもある「ボトムアップ理論」というわけ。
つまり自分で考え自分で行動する。自己解決能力を磨く……それで選手のやる気を引き出し、組織全体の効果を高めていく。言葉にするのは簡単だが、それを実践するのは並大抵でない。
子どもが自ら考えて行動する力を引き出す 魔法のサッカーコーチング ボトムアップ理論で自立心を養う
畑が重視する選手、そして家族との対話。
結局多くの名将と呼ばれる監督の著書を紐解といても、結局質の高いプログラムを「どうやってやらせるか」、あるいは「質の高いプログラムとは何か」に結論付けられていることがほとんどなのだ。「ボトムアップ」とは「トップダウン」の反対であるとは本書にあるとおり。
読み進めていくと、その思想がまず教育論をベースにしていることがわかる。サッカーコーチとしてよりも、ひとりの教師としてのふるまい、導く力。
それは広島大河フットボールクラブの恩師、浜本敏勝の哲学であるらしい。陳腐であるから浜本が育成した選手の名前は省くが、それは日本サッカー史に残る選手である。
ではいかに「トップダウン」なくしていかに選手を育成するのかに興味がそそられる。それは与えず、否定せず、あくまで中立の立場で選手に問いかけることとしている。それは強制でなく、いわゆる提案であるわけだ。
(関連書籍:広島観音サッカー部は、なぜ強くなったのか―知将畑喜美夫監督の育成システムを大公開 (ザメディアジョンMJ新書) 新書 – 2009/12/21伊藤 和之)
しかし、畑が生徒の家族との対話を大事にしている、というのは驚かされる。訳知り顔の親御さんについて否定する指導者も多い。
強豪校の中には、そもそも家族との対話をしないと決めつけるところもあるのだ。家族の対話を重視するのか否定するのか。少なくとも家庭との対話を重視する監督に尊敬が集まる世の中であってほしいと僕は願う。そして畑は選手のサッカーノートを「交換日記」と表現している。それはコミュニケーションツールとのことである。
「週2回の練習で強化」を可能にする科学的トレーニング。
結局のところ、「ボトムアップ」とはどうしたらそうなるように仕向けるのか、という事なのかもしれない。無秩序な選手にいかに秩序をもたせるか……。
広島観音高校の練習が週2回というのも驚きだ。実際は土日に試合があるだろうから週4の活動なのだろうが、それで全国制覇ができるならそうしたほうがいいに決まっている。
それにはどうも、彼が実践する脈拍トレーニングとも関係がありそうだ。細かい数値は本書に任せるが、それも畑は隠すことなく本書で与えてくれている。強豪チームのトレーニングマッチ、リーダー育成論、創造性ある選手とするためのコーチング、リアリティ。
(参考教材:サッカー 教材 DVD 量より質を求めて育成する「脈拍トレーニング」~週2回の練習でも選手をグングン上達させる練習法~畑 喜美夫)
一見すると野放図になりそうな畑の指導論が「どういう風にしているか」でなく「どうしたら実践できるか」を分かりやすく解説している。
多くのサッカー本が「どういう風にしているか」だけで終わる中、その実践まで解説している書籍は稀有。人生を変えうる可能性がある書籍だと思う。つまりもし指導者がこれに触れれるならば、選手たちの人生を変える可能性を秘めるということ。結びの一言も見事である。良書。
■本書で得られる知見
- ボトムアップ理論の構築方法
- 選手との中立な対話の秘訣
- 脈拍トレーニングの実態
- リーダーの育成方法
- 広島観音は格上としか練習試合をしない
(細かい内容はぜひ本書でお確かめください)