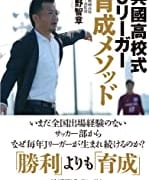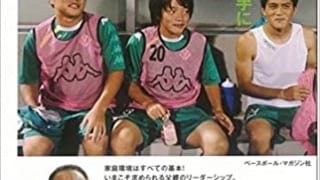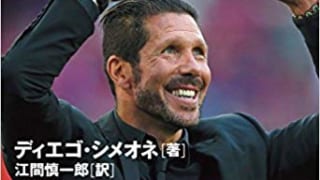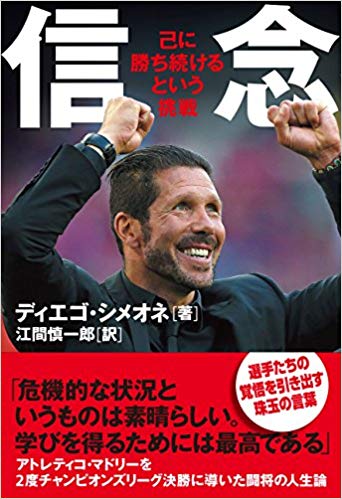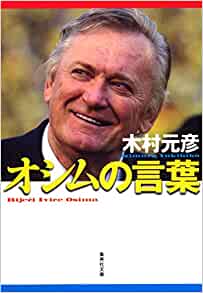選手時代は当時世界最高峰だったセリエAやアルゼンチン代表。1998年フランスワールドカップでは執拗な威嚇の末ベッカムを退場に追い込んだり、ドサクサ紛れに中西永輔へアイアンクロー(というかほとんど目つぶし)をぶちかます「潰し屋」として大活躍し、引退はアトレティコ・マドリーの監督として二つの某メガクラブと真っ向勝負を演じるディエゴ・シメオネ。
彼のおかげでアトレティコは「マドリーのもうひとつのクラブ」あるいは「クン・アグエロとフォルランとトーレスがいた所」から世界的な知名度とファン層を獲得。特にその実践的な守備戦術は時に世界中で賛否を巻き起こしながら欧州サッカーに確固たるポジションを築くことに成功している。なんでもアトレティは世界で最も「効率的に結果を残す」クラブなのだそう。
歯切れよく語られるサッカーの原則。
そんなシメオネの「信念」、著者はシメオネ本人とされており、なんとも力強い言葉尻に満ちている。「目標に近づいているのならば、いくつかのことから遠ざかってもそこまで気に留めることはない」、「もっとも重視するのは立ち向かう情熱である」などとぶちあげる様子は詩人らしくもあるが、むしろ「親分」という表現に近い。しかしなんの注釈もなく唐突にアルゼンチンのプロレス事情が語られるのには参った。
「私はカラダヒアン、皆はラ・マミアになりたかった」といわれても我々ジャポネーゼにはサッパリわからない。うまく意訳するのならば、興行主とチャンピオン同時の立場を好んだという事……。つまり、シメオネは小学生にしてプロレスの仕組みを紐解いていたというのである。彼の親父さんはさぞ難しい顔でサンタクロースに扮したことだろう。
つまりそれは彼が生まれながらのリーダーであり、幼いころからある現象を俯瞰してみることへの証明として語られている。そして、彼のフットボール感が攻守において「スペース」を重視することへと紡がれていく。「情熱・俯瞰・スペース」。並べて言葉にすると、確かにサッカーの原則へとつながる風情がある。
シメオネはまた、本書で語る数少ない選手の中でメッシとブスケツを挙げている。また彼は情熱とともに練習と努力を愛し、監督には謎が必要だとも説いている。
誤解され続けてきたエリートの闇が浮かび上がる。
興味深いのは、シメオネがバルセロナのプレー……哲学を暗に否定していることだろう。シャビやイニエスタが華々しい閃光を放ち続けたスペイン代表の黄金時代とバルセロナのそれはほぼ符合するが、それがフットボールの代名詞になることなどありえない。ではフットボールとは何か? それは努力と情熱で、バルセロナそのものでない。あたり前のように聞こえるが、世界的に「ティキタカ」が採択されていた時代は確かにあった。
やがて本書はシメオネ自身の闇の部分をあぶりだすように綴られていく。それはあることないことをすっぱ抜かれたベッカムとの確執や、彼自身が語る社交性、本質によるものなのだろう。彼は生まれながらのリーダーで24時間働けるファイターではあるが、決してフランクではない。その面影は、選手時代に我々が抱いていたイメージとそう変わるものでなく、そんな彼だからこそ愛され続けてきた。
シメオネの実直な仕事と次なる野望。
しかしシメオネをシメオネたると本書でその個性を際立たせているのは、彼のバランス感覚だ。ヨーロッパの若手の技術をほめたかと思えば、アルゼンチンの若手にはそれに無い個性があると称賛し、ときには色々あったイギリス人の言葉を自身への薫陶にしてみせる。そこには伝記にありがちな「クラブのお姉ちゃんに話したくなる武勇伝」めいたものはまるでない。
本書を「育成論」という観点から見れば「努力と情熱」がその答えとなるし、「戦術論」という観点から見ても単純に「フットボールの原則を捉えること」ということになるのかもしれない。それではシメオネという人間の原則は何か? それはおそらくセレスティ・ブランコだろう。たぶん彼は、アトレティに気を使いながらもうなずいてくれそうな気がする。