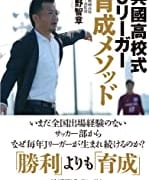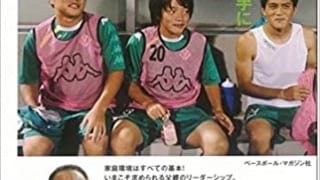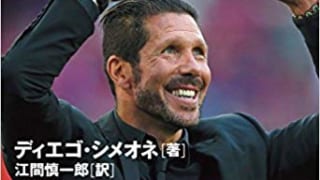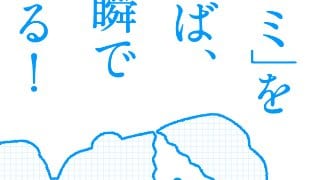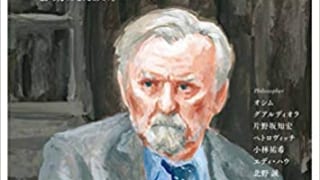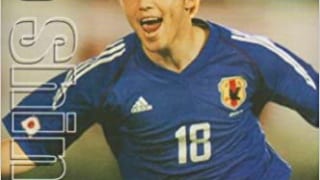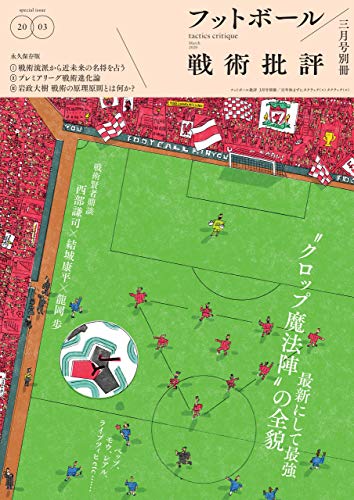Kindleのラインナップを眺めていたら「戦術批評」なる書籍が目についた。戦術を批評……? それってよく考えたら普通のサッカーレポートなんじゃないの思ったら負け。表紙にある「百年休まずにタクティク(ス)タクティク(ス)」のテキストはJリーグ百年構想と大きな古時計のオマージュであることが予想できるが、確か大きな古時計って今はもう動かないんじゃなかったっけ……。ま、Jリーグの発足は1992年だから百年後は2092年。百年構想シンボルマスコットのMr.ピッチはそのときも健在なのだろうか少しもの思う。
巻頭特集は西部謙司による大コラム。テーマは「戦術が個を超越する日はやってこない?」ときたから驚いた。戦術本なのに、戦術の否定から入ってしまう。それってどこの第二次UWF?と思ったが、よく考えたら「戦術を批評」するのだからテーマからまったく逸脱していないし、バルセロナとジェフ千葉のイメージが強い西部謙司がレアル・マドリーを書いたと考えると、その希少性さもありあんといった趣も。この辺りは別冊ならではの魅力といったところだろう。アディダスのジャージを鼎談で着こなす西部の姿を見たら、きっとトルシエは怒ると思うがここはパリじゃないから大丈夫。
進化するサッカー戦術。進化するサッカークラスタ。
続いて本書はクロップの戦術を図解を交えて紐解いていく。中でも、らいかーると氏の「相手がボールを持ってほしいなら持たなきゃいい」という表現には合点がいった。戦術といえばポゼッションのイメージがつきまとうけど、相手の裏をかくのがつまり戦術というわけだ。
結局のところ、言葉はわかりやすいほど読者には有難いし、伝わりやすい。そのことを再認識させてくれるのがグレアム・ポッター。ブライトンというプレミア下位チームでポゼッションサッカーを実現している気鋭の監督だ。プレミアでは「最近一流の監督が増えてきた」と説く。イタリア人が「プレミアは結局最後の5分は蹴って走る」と揶揄したのは今は昔ということなのだろう。その証明は、本書後半の「プレミアリーグ戦術進化論」に続いていく。そしてマリオ・サポによるサッカー用語の解説はサッカーの原理原則を知る上で非常にありがたい。
本書を通してみると、らいかーると、13才のサッカー分析をはじめとして、いわゆる(少なくともサッカー雑誌業界にとっては)「新鋭」とされる書き手が多い。多彩な活動をみせはじめている岩政大樹もそれとしていいだろう。本書では「クラスタ」という言葉が恐らく意図的に多用されているが、それも含めてサッカーテキスト界隈に新たな息吹を感じさせる一冊でもある。
(新井一二三)