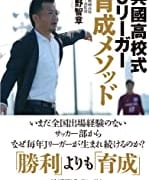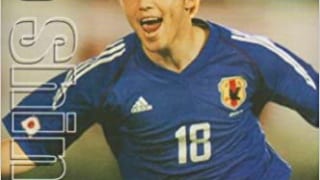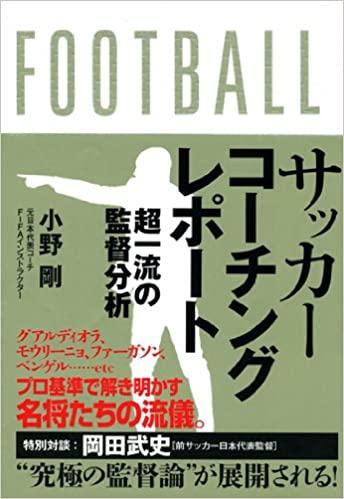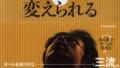彼の友人だというジェラール・ウリエによれば監督には「クビになった監督かこれからクビになる監督」の2種類しかいないのだそう。ちなみに「クビ」の原訳は「sack」で、クビにする従業員の持ち物をズダ袋に渡したことが由来だかなんとか。
市船から筑波大学を経てアメリカ、イングランドでの指導者ライセンスをひっさげJFAの強化委員やサンフレッチェ広島、ロアッソ熊本、FC今治とさまざまなキャリアを持つ小野剛。日本サッカー史に残るキャリアとしては「岡田武史とともにジョホールバルの歓喜を謳った」人物で、その著作は「超一流の監督」を言語化するという意欲的な内容……つまり、これを読めば超一流の監督になれる(少なくともは近づける)というワケである。
それによると超一流の監督は「情熱とあくなき探求心」、「専門的知識」、「マネジメント能力」、「リーダーの資質」を持ち「勝って兜を尾を締める」という。それら個々のエピソードをファーガソンやリッピ、モウリーニョなど歴代の名称に喩えて紹介していく。
中でもモウリーニョに関する記述が多い。小野もモウリーニョも選手時代に輝かしいキャリアがあるわけではない。その威光なしに監督として成し遂げるための何かを探るために、モウリーニョはうってつけというわけなのだろう。
そして中盤にかけて自身が成し遂げた京都サンガのJ1昇格を逸話を交えて紹介するのだが、興味深いのはシーズン途中に解任された4年目の出来事も公平に記事にしていること。「選手でなく自分主導のチームをつくろうとしてしまった」ことがその失敗だったと述懐しているが、そうしたフェアな記述があると、本書に思い入れもしやすいというもの。
終盤にかけて続くトルシエやオシムにまつわる逸話は技術委員を務めた彼なりのボーナス・トラックのようなものだろう。トルシエのエキセントリックな言動は、アフリカでのキャリアからくるトラウマとほのめかす記述には、なるほど思いあたるフシもある。彼はずっと恐れていたがゆえに、奇人を装っていたということだろう。そしてオシムは「日本代表の仕事は、どうしてもやりたかったのだ」と告げた。オシムのほうがトルシエよりもその記述が圧倒的に多いのがなぜか勘繰るのは大人の悪いクセというもの。
そして巻末の岡田武史との対談はボーナス・トラック第二弾というわけ。文中にある岡田武史とカペッロの確執は「日本は4-1-4-1の真似事をした9-1」と言われたのが理由らしい。おまいう……。ちなみに岡田武史は本文中にサッカー本についてある仮説を唱えている。いやいやいやいや!
ちなみに小野この対談ののち、岡田とともにに杭州緑城足球倶楽部へと旅立っている。FC今治の監督を経て小野剛が目指すものには……ある頂が思い起こされる。
(新井一二三)