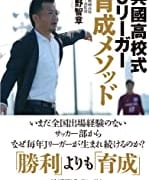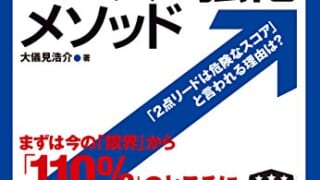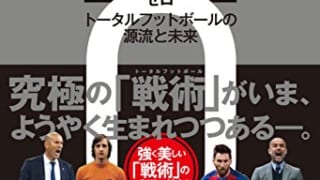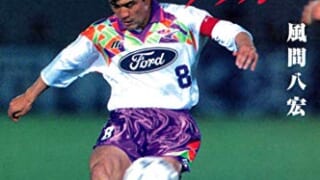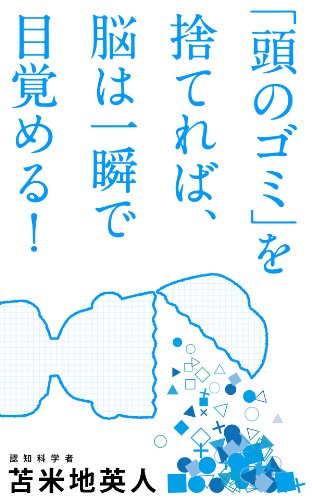油断していたらサッカー村民がピリつく言葉も交えて来た。
ゴールと関係ないものはゴミ。さすがにベストセラー作家、読者をひきつけるすべを知っていて、論点をわかりやすく提示する。最終地点に向かうもの以外は「ゴミ」というわけで、それを捨てれば脳はシンプルに動かせる。つまり僕らにとってのゴミとゴールは……。
◇
知ってる人は知っている、知らない人は誰も知らない。
著者の苫米地英人はカーネギーメロン大学の博士で聖マウリツィオ・ラザロ騎士団大十次騎士。公益社団法人日本ジャーナリスト協会会長兼理事長かつジョージメイソン大学の客員教授。
とにかくよくわからないがすごそうな人、という言葉がしっくりくるけど、とにかく脳科学におけるベストセラー作家であることは確からしい。
オシムはかつてコーチングについて「ほかの競技のやり方も見ろ」と言っていた。
確かにサッカー村の村民は鎖国を紐解くべきだろう。
なにしろ「頭のゴミ」を捨てれば脳は一瞬で目覚めるそう。
サッカー的に言えば難しすぎる指導ということだろうか。ハーフタイムで選手が覚えていられる指示はせいぜい2個か3個らしいから、それとも関係があるのかもしれない。
脳科学者の著作と聞いて、なにやら難解そうだなぁと覚悟していたら、いきなりQ&Aのざっくり文体。99%の読者が言い当てない回答を示しておいて逆説的に読者をひきつけるトリックから始まった。正直読みやすいなら何でもいいけれど、
「やる気スイッチは必要ない」
なんてスクールIEを刺激しそうなキャッチコピーも面白い。
むしろ脳科学本の衣をまとい、刺激的な言葉が読者をひきつけていく。
感情的な人の脳はサルやゴリラレベル。
おいおい、あそこの指導者の脳はサルやゴリラレベルなのかよ……。
僕には口が裂けてもそんなことは言えない。苫米地英人かく語りき。
どうやらイライラしていると行動が感情に支配されてしまうということらしい。
なんとなく襟元を正したくなるような気もする。自分を俯瞰してみよう、そういうことか。
ゴールと関係ないものはゴミ
ひるがえってコーチの指導はどこまでがゴールに向かってどこからが無駄なのか。
量は質を担保して、質なき量は効果を下げる。それをなすべきビッグデータは? あくまでサッカーのために僕らは考える。
感情は人としての幅を広げる。
ならばモウリーニョやクロップは正しいということになる。しかし彼らは選手を言下に否定したりはしない。
そしてゴールに無意味な感情は捨てて、ゴールに意味のある感情だけを味わえという事らしい。
なんだか少し仏教的な記述だなぁと思ったら、中盤からそのもの仏教的価値観を薦められる。
たしかにそれは日本人が捨てたロストテクノロジーなのかもしれない。
肩書が長すぎるのは、彼にとってむしろ逆効果ではないか。
何しろ太字だけ読んでいれば内容の7割は分かった気になれるし、ある種の悩みも解決してくれそう。残った細字は後日読めばいい。
置き換えて自分の襟元を正せる良著。
総括すれば、軽く読めてためになる、ということなのだろう。
コーチは「価値観の創出」が目的だと断言してさえもいる。
そして、自分の未来が最高であると確信していれば、過去の自分も今の自分も最高の自分になる。
できるかできないかはわからないが、なんとなく共感できる一文である。星5点。
(新井一二三)
(細かい内容は本書でぜひどうぞ!)
■本書で得られる知見
・自分ができると思い込むとスッキリする。
・失敗したことは思い出さない方がいいらしい。
・やる気をそぐ約束事は作るな。
・ゴールがあればゴミはなくなる。
・コーチの目的は「価値観の創出」。