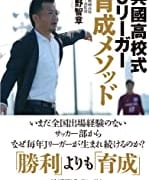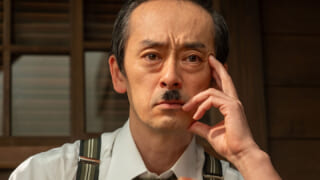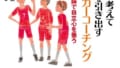こんにちは、新井一二三です。今回は西部謙司著、「サッカー日本代表アナライズ」を紹介します。サッカージャーナリスト界のトップランナーであり戦術批評家としても知られる西部が日本代表の歴史を軽妙な解説に主観を混じえて語るこの一冊。質、量ともサッカー本において屈指の大著であるため、複数回に分けて紹介できればと思います。
◇
かつて日本代表は北朝鮮、中国、そして韓国といったアジアの列強に対してフィジカルで勝負にならない時代があった。しかし西部はむしろフィジカルは強いという。
というより、圧倒的なフィジカルはない、という表現が正しいのだろう。日本からドログバやビエラは現れないが、メッシ「タイプ」の選手はおそらく出てくるかもしれない。少なくとも日本がある種のフィジカルに秀でていることは、興国高校の内野智章も記しているとおりである。
また西部は1998年、グループリーグ三連敗で結果だけ見れば惨敗した当時の日本は、勇敢で臆するところは微塵も見られなかった、と評している。つまりメンタルもある、ということ。
日本がワールドカップに出場してから20年以上の年月が過ぎた。本書はそんな記憶の靄の中に消えゆく日本サッカーの歴史を紐解き、将来への戦い方のヒントを見据えようという意欲作。
日本代表の試合の中で特に重要とする22試合をピックアップするという試みだ。
マリウス・ハンス・オフトが日本にもたらしたものとは。
日本代表を強化するには外国人監督しかないが、当時のJFAの懐事情では高名な監督を呼ぶなど夢のまた夢。マツダでの年俸が1500万円以下だったから契約できた、というハンス・オフトはしかし確かに日本サッカー界に新風をもたらした。
西部はそれを「日本代表に論理と秩序をもたらした」と表現する。オフトが日本にもたらしたそのコンセプトは「ディティール」だった。
■オフトが日本にもたらした「ディティール」
- トライアングル
- コンパクト
- スリーライン
- アイ・コンタクト
- ノー・スクエア・パス(横パス禁止)
オフトによると、「ディティール」とは基本とのこと。それにはどうも哲学的な意味合いもありそうだ。
日本にこうした「簡単な言葉でサッカーを伝える」文化をもたらしたオフトの功績は大きい。その言葉は、メディアとたどってサッカージャーナリズムの定型フォーマットをも作り出した。
本書によると、オフトは「3トップを45分は無理」と考えていたらしい。ここでいう3トップとは昔ながらの両ワイドが「守備できないウイング」のという意味だろう。その急先鋒は今の名将、長谷川健太だったというのも興味深いが、そしてオフトはけが人を出しながらも土壇場で北朝鮮、韓国を破り運命の「ドーハ」へとたどりつくことになる。
(詳しい内容はぜひ本書でどうぞ!)
韓国相手にカズと松永が魅せる!そしてオフトジャパンのクライマックス、ドーハへ。
「ドーハの悲劇」は100年でも200年でものちに語り続けられる「日本サッカー界の始まり」だ。その一戦で、ラモスは日本寄りな判定を見抜いて中山へのラストパスをあえてオフサイドギリギリのところまで待って出したという。
しかし、ラストプレーで時間稼ぎという判断ができず、軽率なパスを敵に与え、コーナーキックを許したのもまたラモスであった。
だが西部は、その敗因を当時ダイナモとして中盤を縦横無尽に走り回っていた北澤を投入できなかったことにある、としている。
当時中東の選手が「痛がって」顔を抑えて倒れこむのが向こうの「常套文句」であることなど当時自分たちは知りもしなかった。しかし西部によると、このドーハでの一線ではイラクの選手たちも各々が叱咤し、鼓舞したという。
総括すれば、オフトジャパンは37歳のラモスに始まり、ラモスに終わったのかもしれない。オフトジャパンはまた、日本に戦術に「ディティール」をつたえたが、それゆえに見破られやすく、戦術的に後手を踏んでいたのも確か。
柱谷が本書である言葉を使って言うように、結局日本のレベルはまだひな鳥だった、ということなのかもしれない。しかし、西部も言うようにオフトはメディアを巻き込み日本のサッカー界をのものを大爆発させた。それを「開闢」と例えることを自分は自分はためらわない。
ファルカンは早すぎたのか、そもそも無能だったのか。
オフト後の日本を託すのは誰か。オフトは固辞し、磐田へと渡った。テレ・サンターナに接触はしたようだが、「10億よろしく」と足元を見られ、結局パウロ・ロベルト・ファルカンに収まった。
ファルカンといえば、何しろブラジルの伝説「黄金の四人」の一角である。西部は協会が彼を選んだ理由を「修羅場をくぐっている人物だから」と残しているが、僕たちが思い出す彼のイメージはすこぶる悪い。弱きに強く、強きに弱かったアギーレ、屈指のタレント時代を中くらいにしたジーコと比べてもそれは出色である。
アギーレはアジアカップ予選リーグを無失点突破。ジーコは劇的なワールドカップ出場を決めている。アギーレもジーコも少なくとも、見る者に感動を与えた瞬間は確かにあった。しかしファルカンにはまるでそれがない。しかし西部によると、実情は少し違っていたという。
日韓戦での厳しい追及がファルカンの運命を狂わせる。
ファルカンにはブラジル代表監督の経験があった(主な成績はコパ・アメリカ2位)。マツダ以外でさしたる監督経験がなかったというオフトとは、少なくともキャリア面では雲泥の差があるといえる。
引き分け、引き分け、勝利。ドーハを包んだ熱狂から比べれば歯がゆい内容でアジア大会の予選を突破した日本。準々決勝で韓国に挑んだファルカンは、後半の3得点で勝利を挙げている。日本にとってはそれだけ切ない敗北だったわけ。
しかも数字上こそ一点差だが、内容は澤登(岩本)と遠藤昌浩が守る左サイドをノーガードで破られ続ける完敗だった。
西部によるとこの当時のファルカンはイタリアで解説を務める「最新鋭プレッシング」通だったそう。それを始めるのには早すぎたとする向きもあるが、少なくともこの試合においては相手が悪すぎた。
ホン・ミョンボ、ユ・サンチョル、ファン・ソンホン、コ・ジョンウン。キャリアの絶頂期にあった前園は輝きをみせたが、あまりにも役者が違いすぎた。そもそも止めてけるの技術も圧力もまるで違う。
とはいえ、西部はある理由をつけて、そもそもファルカンに選手を見る目がなかったのではないかとも言っている。
そしてファルカンは日本に何を残したのか。とりあえず、あまりにも覇気のないファルカンのふるまいは、監督のモデルとして物足りないのも事実かなと思う。
■本書で得られるファルカン編の知見。
- 近年まれにみる日韓戦惨敗の様子と選手の証言。
- 世代交代の難しさ。
- プレッシングの導入
(この項目続く)
(詳しい内容はぜひ本書でどうぞ!)