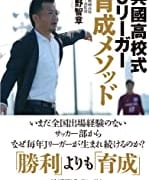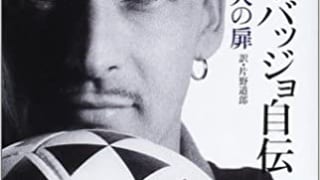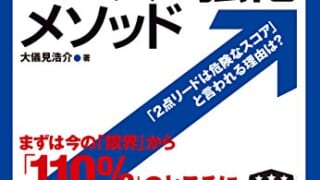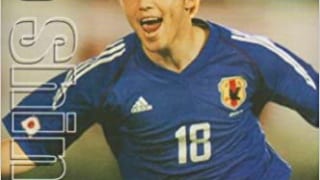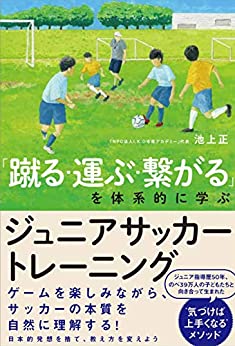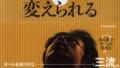「ドイツにはドリブラーという言葉がない」とドイツ留学の経験を元に語るが、だからドイツにはドリブラーがいないことへの証明ではないのか。
ジュニア指導歴50年、ジェフ千葉や京都サンガの育成普及部を歴任、ベストセラー「サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法」などで知られ、ジュニアサッカー保護者向け情報サイト、「サカイク」や「ジュニアサッカーを応援しよう!」のコラムでもよく知られる池上正による育成本。ちなみに祖母井秀隆は大阪体育大学の先輩で、千葉やジェフでも行動を共にしている模様だ。
親御さん世代に抜群の知名度を誇る池上正だから、その一言一言が日本サッカー界に浸透してしまうという重責がある。その重責の核となるのが「サッカーはチームスポーツだ」とする彼なりの哲学。その哲学に沿って、小学校低学年年代で一対一やドリル練習を否定してしまうのだから正直驚いた。育成年代の現場を体感してきたコーチならば個のレベルアップなくして選手のレベルアップはないと知るはず。周りが見れようが声が出せようが、一対一や止める蹴るで劣る選手が素晴らしいと認められることなどありえない。
どうやら本書ではそれに対する回答はなさそうだ。ドイツで成功している日本人の多くはいわゆる「ドリブラー」だし、チームで守る文化がないからこそドイツは一対一の文化が根付いたのではないか。日本とドイツの良さ両方を消してしまわないのかと読み進めるごとに不安は募る。彼は一人で複数人抜いてしまうようなドリブラーに、周りを使うように教えるのだそうだ。その場合、せっかくのドリブラーの卵が消えてしまうのではないかと率直に思うのだが……。
とはいえ、複数人でするトレーニングメニューを言葉と図解で解説する手際はさすがに秀逸。特にジュニア年代におけるコーチの教科書としては非常に有用だろう。ジュニア年代の最終形が4対4だとする説にも非常に合点がいく。そしてGKが加わって数的優位を作るというのも非常に論理的だ。
また、子供に対する接し方、ディベートに対する記述も「子供を認めてあげる雰囲気を」など分かりやすい言葉で非常に整理されていており、このあたりはさすが。「11の魔法」でベストセラー作家となった氏の手腕がみなぎる。
結局、サッカーは進化している。サッカーは陣地取りだとする時代は斜陽をみせ、プレスとカウンター……そしてアフターコロナの時代が始まろうとしている。その中で指導者はどのように育成本を読み解くのか。2019年7月の初版。それでも時間と共に子は育つのだから。
(アラヰフミ)